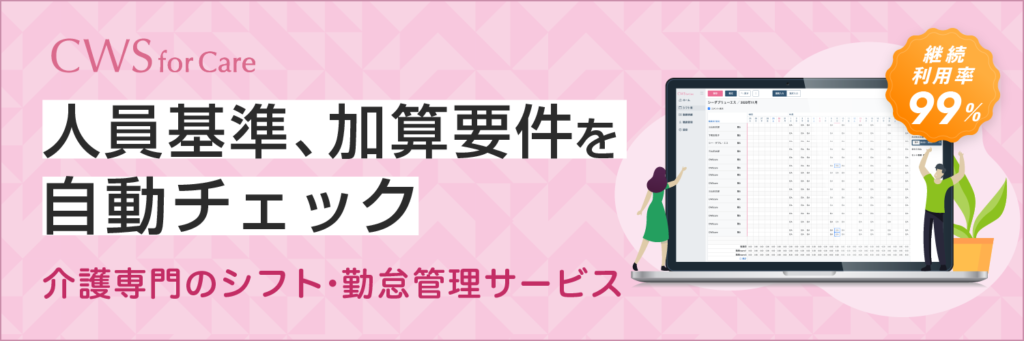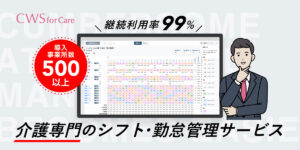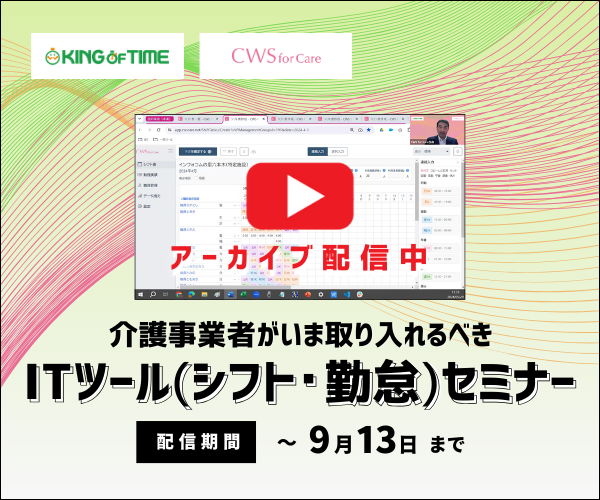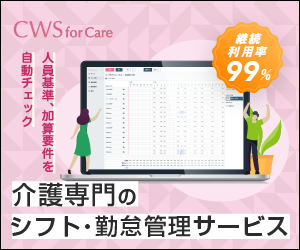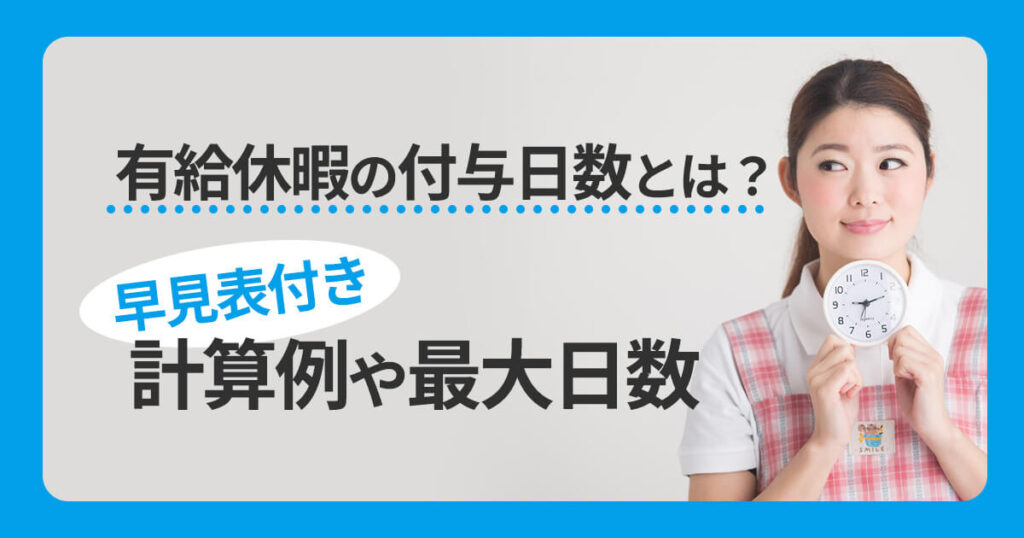
日本における休暇取得率の低さから、年5日の年次有給休暇の取得が義務化されました。企業側は労働者の有給休暇付与日数や、取得日を正しく管理・把握し、法令を遵守することが求められます。
この記事では正社員の有給付与日数をはじめ、アルバイトやパートなど短時間労働者に対する付与日数や、有給が発生するタイミングなどを表でわかりやすくまとめました。
介護事業所の面倒なシフト・勤怠管理がらくらく
人員基準や加算要件は自動でチェック!CWS for Careはシフト表作成、勤怠管理、勤務形態一覧表作成をワンストップで提供する、介護専門のシフト・勤怠管理サービスです。
⇒ 「CWS for Care」公式サイトへアクセスして、今すぐ資料を無料ダウンロード
目次
【早見表付き】年次有給休暇の付与日数のルール
年次有給休暇は正社員、短期労働者に関係なく、以下の2つの条件をどちらも満たすすべての労働者に付与されます。
労働者に有給休暇を付与するのは、企業側の義務です。企業は労働者の勤務状況を把握し、漏れのないように有給休暇を与えてください。次に正社員と短時間労働者それぞれの付与日数を解説します。
正社員の有給休暇付与日数(早見表)
正社員における有給休暇付与日数は、勤続年数によって変わります。管理監督者のほか、契約社員や嘱託社員などの有期雇用労働者なども以下のルールに基づいて計算します。
| 継続勤務年数 | 半年 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
上記のように、勤続年数が増えるごとに付与できる日数が増加します。たとえば2023年6月に入社した社員の場合、2023年12月時点で10日間の有給休暇が付与されます。さらに、そのまま継続して同じ会社に勤務した場合は、2024年6月時点で11日間の有給休暇が付与される計算です。勤務年数が6年半になった時点で付与できる日数の上限は20日間で、これ以上は増えません。
ただし、あくまで最低日数のため、福利厚生の一環として上記より多い日数を付与することも可能です。
アルバイトやパートなどの有給休暇付与日数(早見表)
アルバイトやパートタイマーなどの短期労働者の場合、労働日数によって有給休暇の付与日数が変わります。
| 所定労働日数/週 | 所定労働日数/年 | 継続勤務年数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 | |||
| 付 与 日 数 |
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
上記のルールに基づくと、2024年5月から週3日勤務で働き始めたパートタイマーの場合、2024年11月時点で5日間の有給休暇が付与されます。
所定労働日数を週で定めていない労働者の場合は、年間の所定労働日数を数えて計算します。1年半の勤務実績があり、年間85日間の勤務が定められている労働者の場合は4日です。ただし労働日数が不定期な場合は、前年実績を用います。初年度は、半年間の勤務日数を2倍にして計算します。
有給付与日数の計算に関するルール

有給休暇の付与日数を計算するには、勤続年数や出勤率などのルールや計算方法について正しく理解しておくことが大切です。押さえておきたいルールについて解説します。
勤続年数の数え方
有給休暇付与の条件として6ヶ月以上の勤続年数のルールがあります。勤続年数とは、1つの会社で働く在籍期間のことです。たとえば2024年1月に入社し、同じ企業で働き続けた場合、2025年1月には勤続年数1年と数えられます。
ここで押さえておきたいのが、有給休暇付与のもうひとつの条件である出勤率との関係です。出勤率が8割に満たない年でも、同じ企業で働いている場合は、勤続年数としてそのまま途切れずカウントします。
また、定年退職者を引き続き委嘱職員として雇用し直した場合も、勤続年数として継続してカウントしてください。
出勤率の計算方法
出勤率とは、就業規則などで定められている所定労働日数のうち、出勤した割合を指します。計算式は「出勤日数÷所定労働日数×100」です。たとえば所定労働日数が240日で210日出勤した場合、「210÷240×100」で出勤率は87.5%となります。
出勤率が80%に満たない場合、翌年の有給の付与日数は0日となるため、注意しましょう。翌年の出勤率が80%を超えれば、翌々年の有給休暇は勤続年数に基づき付与されます。
なお、有給休暇取得日や産休、介護休業、業務上のケガなどで休業している期間は出勤日数として数えます。店舗の改装や工場の設備不良など会社都合で休業が生じた場合、その期間は所定労働日数に含みません。
年次有給休暇の使用期限
年次有給休暇の使用期限は、付与した日(基準日)から2年間です。2024年4月1日が入社日の社員の場合、一般的には半年後の2024年10月1日が基準日となり、2026年3月31日まで付与された有給休暇が使えます。
前年度に消化できなかった分は、翌年度に使用することができます。ただし、年5日の有給休暇を労働者に取得させることが義務付けられているため、たとえば11日間の有給休暇が付与された場合は、残りの6日間が翌年に繰り越せる計算になります。
【計算例】正社員5年目の有給休暇付与日数
ここでは正社員となって5年目の社員を例に、有給休暇付与日数の計算の仕方を解説します。仮に2019年4月入社だった場合、付与日数は以下のとおり推移します。
| 継続勤務年数 | 半年 (2019年10月時点) |
1年半 (2020年10月時点) |
2年半 (2021年10月時点) |
3年半 (2022年10月時点) |
4年半 (2023年10月時点) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 63日 |
5年目を迎えた2024年4月時点での付与日数の合計は、単純計算で63日となります。しかし、最低でも1年に有給休暇を5日間取得しなければならないうえ、有給休暇の有効期限(2年)などもあるため、実際には以下のように有給の日数は変化します。
| 継続勤務年数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 |
| 繰り越し日数 | – | 5日 | 6日 | 5日 | 10日 |
| 有給休暇取得日数 | 5日 | 10日 | 13日 | 9日 | – |
| 残日数 | 5日 | 6日 | 5日 | 10日 | 26日 |
上記の例だと、5年目の時点で26日の有給休暇が残っている計算になります。
年次有給休暇の最大日数は?
正社員の場合、1年あたりの年次有給休暇の最大付与日数は20日間です。勤続年数が6年半を過ぎると1年につき20日が付与されることから、最大の付与日数は単純計算で2年あたり40日間です。ただし1年につき5日間の有給休暇の取得義務があるため、最大の付与日数は35日となります。
つまり、有給休暇の付与日数が35日を超えている社員がいる場合、有給休暇の取得が正しく行われていない可能性があります。有給休暇は2年間の使用期限があるため、福利厚生などで1年につき20日以上の有休を付与している場合以外は、基本的に35日以上を超えません。
労務管理の担当者は社員の有給休暇取得状況を正しく把握し、必ず社員1人あたり年5日間の有給休暇を消化させてください。
有給休暇取得義務に違反した場合の罰則
企業側が以下の行為をした場合、罰則の対象となります。
| 年5日の有給休暇を取得させなかった | 30万円以下の罰金 |
|---|---|
| 時季指定について就業規則に記載していない | 30万円以下の罰金 |
| 労働者の希望する時期に有給休暇を与えなかった | 30万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役 |
そのほか、有給を取得した労働者に対し給与や昇進に関して不利な扱いをしたり、逆に取得しない労働者を賞与などで優遇したりする行為は禁止されています。
年次有給休暇の時季指定の方法
企業はすでに5日以上の有給休暇を取得している労働者を除き、時季を決めて年5日の有給休暇を取得させなければなりません。
時季指定は労働者の希望の日程を聞き、取得日を決定する方法です。希望日のヒアリング方法は対面でもメールでも可能で、企業側はなるべく労働者の希望に沿った時期に有給休暇を取得させることが求められます。ただし正常な運営が妨げられると企業側が判断した場合は、時季変更権を行使できます。
前述したとおりすでに5日間の有給を消化している労働者には時季指定を行えません。労務管理の担当者は有給の取得状況をチェックし、基準日から一定のタイミングが過ぎたタイミングで、有給消化率が低い労働者に時季指定の声かけをするとよいでしょう。
労働者の有給休暇付与日数や取得日をしっかり把握しよう

法令を遵守するためには、労働者の有給休暇付与日数や、取得日を正しく管理・把握することが必要です。特に有給休暇の取得が年5日を満たしていない場合は、罰則の対象となります。有給休暇の付与日数が異なる正社員から短期労働者まで、漏れなく管理するためには、便利な勤怠管理システムなどを活用するのも1つの手です。
介護専門のシフト・勤怠管理サービス「CWS for Care」なら、有給休暇管理(外部サービス連携)をはじめ、人員基準や加算の自動チェックができるシフト作成機能や勤務形態一覧表の自動作成機能が備わっています。ぜひお問い合わせください。