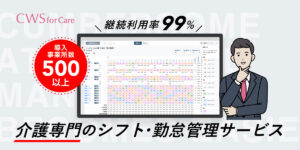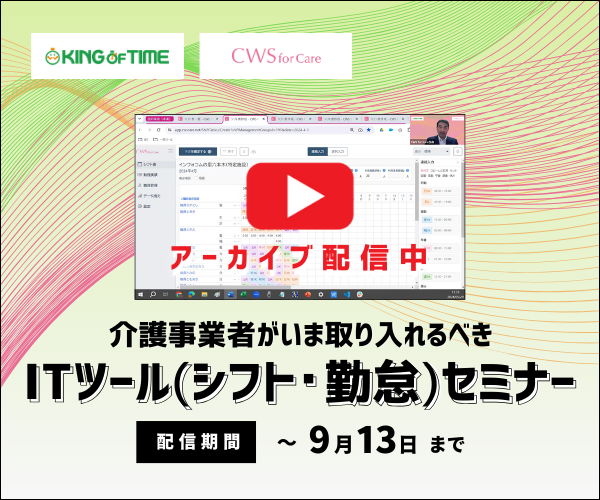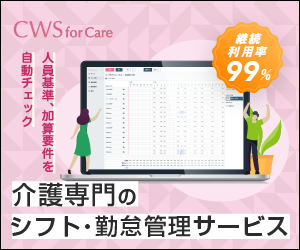個別機能訓練加算とは、利用者に対し個別の機能訓練を計画および実行し、かつ定期的な効果を測定する事業所が算定できる加算です。令和3年度の介護報酬改定で新しい区分として個別機能訓練加算Ⅱが新設され、LIFEの活用が要件に加わりました。
この記事では、加算ⅠとⅡの違いや介護サービス種別ごとの算定要件をわかりやすくまとめました。あわせて算定の流れも詳しく解説します。
介護事業所の面倒なシフト・勤怠管理がらくらく
人員基準や加算要件は自動でチェック!CWS for Careはシフト表作成、勤怠管理、勤務形態一覧表作成をワンストップで提供する、介護専門のシフト・勤怠管理サービスです。
⇒ 「CWS for Care」公式サイトへアクセスして、今すぐ資料を無料ダウンロード
目次
個別機能訓練加算とは

個別機能訓練加算とは、利用者ごとに機能訓練を計画立案および実行し、かつ定期的にその効果を評価する取り組みを行う事業所が算定できる加算です。個別機能訓練加算の対象となるサービス種別は以下のとおりです。
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
令和3年度の介護報酬改定では、区分の変更に伴い、算定要件や単位数の見直しが行われました。LIFEの活用が必須の区分が新設されたため、算定要件をよく確認し、理解したうえで実施することが重要です。
個別機能訓練加算ⅠとⅡの違い

個別機能訓練加算の区分はⅠとⅡの2つに分かれており、違いはLIFEの活用の有無です。加算Ⅱは要件を満たしたうえで、LIFEを活用し、個別機能訓練計画の見直しを行う必要があります。。
LIFEとは科学的介護情報システムのことで、全国の介護事業所などから収集したデータをもとに、科学的に介護を実施していく取り組みを指します。厚生労働省が運営するLIFEのホームページから利用申請することで、システムを利用できます。
個別機能訓練加算Ⅱでは、個別機能訓練計画などの内容をLIFEに提出し、フィードバックを受け、計画の見直しを行う一連の流れが必要です。
なお、加算ⅠとⅡは併算定ができます。
個別機能訓練加算の算定要件と単位数
介護サービス種別ごとに、個別機能訓練加算の算定要件と単位数をまとめて解説します。
通所介護(デイサービス)の場合
| 算定要件 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算Ⅰ |
|
専従の機能訓練指導員※を1人以上配置 ※配置時間の定めなし ※人員基準で配置している機能訓練指導員で構わない |
(イ)56単位/日 |
| サービス提供時間を通じて、専従の機能訓練指導員※を1人以上配置 ※人員基準で配置している機能訓練指導員に加えて、1人以上の配置が必要 |
(ロ)85単位/日 | ||
| 個別機能訓練加算Ⅱ |
|
20単位/月 | |
上記には、地域密着型通所介護も含まれます。加算Ⅰは(イ)と(ロ)に分かれており、機能訓練指導員の配置基準が異なります。(ロ)では人員基準を超える機能訓練指導員を配置することで、より細やかで質の高い機能訓練の実施を目指すことができます。
(イ)と(ロ)の併算定は不可ですが、それぞれに加算Ⅱを合わせて算定することができます。すでに(ロ)を算定しており、機能訓練指導員が1人公休などで不在の場合には、その日は(イ)を算定してください。
利用者に対する説明は直接居宅に伺う以外に、テレビ電話などを活用することも可能です。テレビ電話での説明に関しては、個人情報の適切な取扱いに留意し、利用者とその家族の同意を得たうえで、厚生労働省のガイダンスなどを遵守しながら実施してください。
介護老人福祉施設(特養)の場合
| 算定要件 | 単位数 | |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算Ⅰ |
|
12単位/日 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ |
|
20単位/日 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護も算定可
特定施設入居者生活介護施設の場合
| 算定要件 | 単位数 | |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算Ⅰ |
|
12単位/日 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ |
|
20単位/日 |
※介護予防特定施設入居者生活介護も算定可
短期入所生活介護施設(ショートステイ)の場合
| 算定要件 | 単位数 | |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算 |
|
56単位/日 |
個別機能訓練加算の注意点

個別機能訓練加算を算定する際には、機能訓練指導員による機能訓練が必要となります。機能訓練指導員が特定の曜日や時間帯にしか配置できない場合は、算定要件を満たしていないため、その日は算定できません。機能訓練指導員から機能訓練を受けた利用者のみ算定します。
機能訓練指導員として配置できる人員は、以下の資格を有する者です。専従での配置が求められますが、常勤・非常勤は問いません。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師※
- きゅう師※
※機能訓練指導として6ヶ月以上の経験があり、かつ事業所ではり師およびきゅう師以外の資格を持つ機能訓練指導員を配置している場合のみ
看護職員を機能訓練指導員として配置する場合、人員配置基準においては看護職員の配置時間に関する規定がないため、看護職員として業務に従事していない時間帯は、個別機能訓練加算の機能訓練指導員として配置することができます。また、地域密着型通所介護事業所(定員10名以下)で人員配置基準を介護職員ではなく看護職員により満たしている場合も、兼務が可能です。
なお、機能訓練の内容を施設サービス計画などに盛り込む場合は、個別機能訓練計画として新たに作成する必要はありません。
個別機能訓練加算の算定の流れと必要書類

個別機能訓練加算の算定の流れは、以下の通りです。必要な書類についても次に詳しく解説します。
- 自治体への書類提出
- ケアマネジャーへの説明
- 利用者およびご家族への説明
自治体への書類提出
個別機能訓練加算の算定要件を満たしていることを確認したうえで、自治体に以下の書類を提出します。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 機能訓練指導員の資格証の写し
- 個別機能訓練加算計画書
ケアマネジャーへの説明
算定にあたっては、ケアプランへの位置付けが必要です。ケアマネジャーへ算定要件の説明を行い、必要に応じてケアプラン位置付けの依頼を行ってください。
利用者及びご家族への説明
加算取得にあたっては、利用者に費用負担が発生します。さらに個別機能訓練加算を算定する際には、居宅への訪問が必須となるため、事前の説明が必要です。
専門用語や略語を使わずに、分かりやすく、個別機能訓練を行うことの必要性や効果、実施の流れについて説明を行ってください。
利用者の居宅を訪問し、ニーズや状況の把握
職員が利用者の居宅を訪れ、ヒアリングを行います。「興味・関心チェックシート」を用い、日常生活の希望などを聞きながら、利用者のニーズを適切に把握しましょう。
さらに「生活機能チェックシート」をもとにADLなどの身体機能や、現在の生活の状況について確認してください。ケアマネジャーからも既往歴や実際の生活状況などの情報をヒアリングし、さまざまなな視点で情報収集を行うとより効果的です。
計画書を作成
利用者宅でヒアリングおよび確認した情報をもとに、機能訓練指導員を含む他職種でケアカンファレンスを実施し、計画書を作成します。利用者の現状の暮らしと乖離しないよう、生活に即した具体的な目標を設定することが重要です。ケアカンファレンスでアセスメントの結果などを詳しく共有することで、職員が共通の意識を持ってサービス提供ができるようになります。
利用者とその家族に説明・同意の取得
計画書の内容について利用者とその家族に事前に説明を行い、同意を得てください。利用者が主体的に取り組むことができるよう、機能訓練を行う理由やどんな効果が期待できるかなどを丁寧に説明することが重要です。説明後に、同意を得て、計画書の写しを交付します(計画書はデータで渡すことも可)。同時にケアマネジャーにも説明を行い、計画書の写しを交付してください。
機能訓練を実施
機能訓練指導員が直接、機能訓練を行います。利用者に対し個別に行うか、同じような目標を立てた5人以下のグループで実施することも可能です。機能訓練は、週1回以上を目安に行います。さらに訓練メニューを複数用意し、利用者自身に選んでもらうことで、主体性を育むこともできます。
評価と計画の見直し
定期的に、機能訓練の効果と計画の見直しを行います。日々の機能訓練の記録を事業所内で共有し、他職種でカンファレンスを行うことでより効果的にモニタリングを実施できます。
その評価を利用者とその家族に説明したうえで、訓練の見直しを行ってください。訓練の様子を写真や動画で撮り、共有するとよりわかりやすく、イメージを持って伝えることができます。その際は出席者、日時、話し合った内容などのカンファレンス記録の記載を行うことが必要です。
個別機能訓練加算はPDCAを意識し取り組むことが重要
個別機能訓練加算は、利用者のニーズや生活状況に合わせて個別の機能訓練を計画し、実施した事業所が算定できる加算です。さらに定期的にその効果や方法を評価し、計画の見直しを行うことが求められています。特に令和3年度の介護報酬改定で新設された加算ⅡにおいてはLIFEを活用しながら、PDCAをもとに計画を見直す必要があります。
算定するには算定要件の確認をしっかり行ったうえで、利用者ごとに適切なアセスメントと多職種協働で個別機能訓練計画書を作成し、実施することが重要です。利用者ごと、目標達成につながるよう、計画や実施内容は適切に記録に記載し、3ヶ月ごとに評価と見直しを行うよう心掛けてください。
機能訓練体制についての加算もあります。あわせてご確認ください。